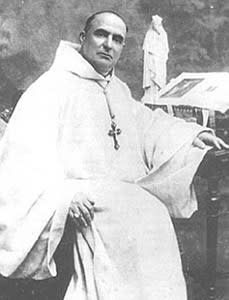アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
1969年9月25日、オッタヴィアーニ・バッチ両枢機卿が、教皇パウロ6世に提出した、新しい「ミサ司式」の批判的研究(Breve Exame Critico del Novus Ordo Missae)の注です。
1 Missa normativa
2 Consilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia
3 non placet
4 juxta modum
5 Missale Romanum
6 Novus Ordo
7 Quo Primum ここで著者は公布の日付を7月13日と書いているが7月14日の誤りなので訂正して訳した。
8 原注1:「私たちのカノンの祈りは既にDe Sacramentis(4-5世紀)という論文の中に見いだすことが出来る。・・・私たちのミサは本質的な変化なしに、最も古代の共通の典礼から初めて発展したその時代にまで遡ることが出来る。このミサはカエサルが世界を支配しキリスト教信仰を地上から消滅させることが出来ると希望したその時代の原初の典礼の香りをそのまま残している。つまり、われわれの祖先が自分たちの天主であるキリストに賛美も歌を歌うために夜も明ける前から集まり祈ったその時代のものである。・・・キリスト教世界全てを見回しても、ローマ・ミサほど崇敬すべき典礼様式は存在しない。」(A. Fortescue神父 The Mass, a study of the Roman Liturgy, 1912)
「今日あるままのローマ・カノンは大聖グレゴリオにまで遡る。今日まで使われている聖体祭儀の祈りのうち東方教会にも西方教会にもこれ程まで太古に遡るものは存在しない。ローマ教会がそのミサを投げ捨てると言うことは、とどのつまり、ギリシャ正教会だけではなく英国聖公会やまだ聖伝の感覚をいくらかでも残しているプロテスタントの目にさえも、真のカトリック教会であるという主張をすることをもはや否定していることを意味するだろう。」(Louis Bouyer神父)
9 "innumeri praeterea sanctissimi viri animorum suorum erga Deum pietatem, hausitis ex eo ... copiosus aluerunt." 日本語訳は、『新しいミサ典礼書』11ページから始まる使徒座憲章の公式日本語訳を参照した。
10 "ex quo tempore latius in christiana plebe increbescere et invalescere coepit sacrae fovendae liturgiae studium."
11 Sacrosanctum Concilium
12 "ut sigularum partium propria ratio necnon mutua connexio clarius pateant."日本語訳は、南山大学監修の『第2バチカン公会議公文書全集』1986年を参照した。
13 De generali structura Missae
14 Institutio Generalis
15 原注2: このような定義をした理由として新しい式次第は脚注を付け、第二バチカン公会議文章の2つの文章を参照しろと言う。しかし、この2つの文章を見てみてもこのような定義を正当化させるのもはまったく見あたらない。
この2つの文章のうちの最初のものは、司祭の役務と生活に関する教令(Presbyterorum Ordinis)の5番から取られている。「...司教の役務執行によって、司祭は天主から聖別されて特別な方法でキリストの司祭職に参与するものとなり、聖なる祭儀の挙行においては、典礼の中で常にわれわれのために自分の霊を通してその司祭としての任務を行うキリストの役務者として行動する。司祭は...特にミサの挙行によってキリストの供え物を秘蹟的に捧げる。」
2つ目は、典礼憲章の33番から取られている。「典礼において、天主はその民に語り、キリストは今も福音を告げている。そして、民は歌と祈りとをもって神に答える。」「なお、キリストに代わって(in persona Christi)集会を司る司祭が神に捧げる祈りは、聖なる民全体と、参加者一同の名によって唱えられる。」
しかし、これらの文章からどうやって新しい式次第によって定義づけられたミサの定義へとたどり付くのか見当が付かない。
さらに、この新しいミサの定義は第二バチカン公会議の与えたミサの定義と抜本的に変わっていることを指摘しよう。なぜなら、第二バチカン公会議の「司祭の役務と生活に関する教令Presbyterorum Ordinis」(5番)には、「聖体祭儀の集会は信者の集いの中心である」"Est ergo Eucharistuica Synaxis centrum congregationis fidelium"とあるのにもかかわらず、新しいミサの式次第では「中心」という言葉が取り除かれ、「聖体祭儀の集会は、信者の集いである」となっているからである。こうして「集会・集うこと"congregatio"」という言葉がミサの定義の地位を不正にも奪ってしまった。
16 "Cena dominica sive Missa est sacra synaxis seu congregatio populi Dei in unum convenientis, sacerdote praeside, ad memoriale Domini celebrandum. Quare de sanctae Ecclesiae locali congregatione eminenter valet promissio Christi 'Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum'(Mt.XVIII, 20)."
日本語の公式翻訳では、sacerdote praesideの翻訳が「キリストを代理する司祭を座長として」と原文にはない言葉が補われて訳されている。日本語に訳した方は、ミサの定義が、あまりにも不十分なので、敢えてこの語を追加したのだろう。
17 cena
18 原注3: トリエント公会議は、次のように主の御聖体における実際的現存を宣言した。「聖なる公会議は、次のことを教え、明らかに絶対的に宣言する。まず第1に、聖体の畏れ多き秘跡において、パンとぶどう酒の聖別の後、まことの天主であり、まことの人である我々の主イエズス・キリストが、パンとぶどう酒という感覚的な外見もとに、真に、現実に、実体的に現存する。」(DS1636)
また、トリエント公会議は、ミサが目に見える真の犠牲であり、象徴的な表現ではないことを宣言した。「我々の主であるイエズス・キリストは、自分の花嫁である教会に目に見える犠牲を残そうと望まれた。…この犠牲によって十字架上でただ一度成就されようとしていた流血の犠牲が眼前に現れ、…その救いの力が、我々の日々の罪が赦されるように適応されるためであった。」(DS1740)
しかも、公会議はいけにえを捧げ、犠牲を執行し、司式する者は、このために聖別された司祭であり、天主の民の集会ではないことを宣言した。「イエズス・キリストは『メルキセデクの位による永遠の司祭』であると宣言し、ご自分の体と血をパンとぶどう酒の形色のもとに、聖父である天主に捧げた。そして、使徒たちにパンとぶどう酒のもとに拝領するように自分の体と血を与え、彼らをその時、新約の司祭として制定した。彼らと、彼らの司祭職における後継者たちに、主は「これを私の記念として行え」という言葉をもって、この犠牲を捧げることを命じた。これは、カトリック教会が常に理解し教えてきたことである。」(DS1740)「『私の記念としてこれを行え』という言葉によって、キリストは使徒たちを司祭としたのではなかったとか、使徒たちと他の司祭たちが、自分の御体と血を捧げるように定めたのでもないという者は、排斥される。」(Canon 2, DS 1752)
さらに、ミサが、単なる十字架の記念ではなく、罪の赦しの力を持つ真実の犠牲であることを宣言した。「ミサの犠牲は、ただ賛美と感謝のためであるとか、あるいは十字架上で行われた犠牲の単なる記念であって、罪の償いのためでないとか、あるいは拝領する者だけの利益になるものであって、生存者と死者のため、罪、罰、償いその他の必要のために捧げられるべきではない、と言う者は排斥される。」 (Canon 3, DS 1753)
更に、次の2つの排斥文も記憶しておこう。「ミサの典文は誤りを含んでいるので、廃止すべきであるという者は、排斥される。」(Canon 6, DS1756)
「司祭だけが聖体の秘跡を拝領するミサは不法であるから廃止すべきである、と言う者は、排斥される。」(Canon 8, DS1758)
19 superamento
20 原注4: 改めて言うまでもなく、もし定義された教義のうち一つでさえも否定するなら、最高位階制度による教導権の不可謬性の原理そのものを否定することになるので、その一つ教義の否定自体ですべての教義は否定されることになる。
21 "eminenter"
22 instituantur et reficiantur
23 tutto illegittima
24 separatamente e in assoluto
25 Actio Christi et populi Dei; Cena Dominica sive Missa; Convivium Paschale; Communis participatio mensae Domini; Memoriale Domini; Precatio Eucharistica; Liturgia verbi et liturgia eucharistica
26 ossessivamente
27 Memoriale Passionis et Resurrectionis Domini
28 原注5: もし、この表現がUnde et memoresと言うミサ中の祈りから発想を得たものだとするなら、この祈りにあるように、ご受難とご復活の後に御昇天を付け加えるべきであった。しかし、この祈りを詳しく研究すると、決して本性を異とする現実をごちゃ混ぜにはしていないことがわかる。いや、この祈りは繊細に、それでいて鮮明に、それらを区別している。「我らは主の幸いなるご受難を思い起こすのみならず、さらには、主の古聖所からのご復活、そして尚かつその栄光ある天への昇天を記憶する(… tam beatae Passioni, necnon ab inferis Resurrectionis, sed et in caecum gloriosae Ascensionis)」となっているからである。
29 詩編40:7-9、ヘブレオ10:5
30 原注6: 「感謝の祈り」(日本語では「奉献文」)と言われている新しい3つの典文は、やはり同じように、強調される部分がずれている。驚くべきことに死者の記念が取り除かれ、煉獄における霊魂の苦しみに関する言及が一切ない。しかし、償いの犠牲は、煉獄で苦しむ霊魂に適応されなければならない。
31 新しいミサのなかで、日本語では「供え物の準備」と言われている。
32 "Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate acceptimus panem (vel vitis) quem offerimus, fructum terrae (vel vitis) et manuum hominum, ex quo nobis fiet panis vitae (vel potus spiritualis)"(このラテン語を日本語に直訳すると次のようになる。「主よ、宇宙の天主よ、御身は賛美せられさせ給え。そは、我らが御身に捧げ奉るパン(或いは、ぶどう酒)は、御身の御恵みによりて我ら受け取り奉りたるがゆえなり。そは大地(或いは、ブドウの木)と労働の実り、そこから、我らのために命の糧(或いは、霊的飲み物)となるものなり。」)
原注7: パウロ6世の回勅Mysterium Fideiを参照せよ。この回勅の中で、パウロ6世は象徴主義の誤謬と同時に「意味変化transignificatio」や「目的変化transfinalizatio」という新説を排斥している。
33 Panis vitae
34 Potus spiritualis
35 原注8: 教父や教導職の文章に、確かに言葉としては見いだされる、言い回しや言葉使いが、それらが持っていた意味や文脈、また教義全体から離れ、それに言及されずに絶対的かつ新しい意味で再び使われている。(例えば、霊的糧spiritualis alimonia, cibus spiritualis, 霊的飲み物potus spiritualis)しかし、このようなことは、パウロ6世の回勅Mysterium Fideiの中で充分に摘発され排斥されたことである。
36 "Deus qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti"
37 "Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clementiam: ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nostra, et totius mundi salute cum odore suavitatis ascendat. Amen."(主よ、我らは御身に救いのカリスを御身の憐れみをこいねがいつつ捧げ奉る。そは、我らと全世界の救いのために、御身の天主の御稜威の御前に、芳しき香りと共に立ち上らんがためなり。)
38 cum odore suaviatis
39 総則49「感謝の典礼の始めに、キリストの体と血になる供え物が祭壇に運ばれる。…教会のため、また貧しい人のために信者が持ってくるか、あるいは道内で集めるかした献金または他の捧げものも奉納される。」
40 原注9: このことは、第2バチカン公会議の典礼憲章48番の規定と明らかに矛盾している。
41 prex eucharistica
42 "ut tota congregatio fidelium se cum Christo coniungat in confessione magnalium Dei et in oblatione sacrificii."
43 "Nunc centrum et culmen totius celebrationis initium habet, ipsa nempe Prex eucharisitica, prex scilicet gratiarum actionis et sanctificationis."
44 Suscipe, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, hanc immaculatam hostiam quam ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentiis meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus christianis vivis atque defunctis: ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam.(聖なる聖父、全能永遠の天主よ、私のまことの生ける天主である御身に、私の無数の罪と犯罪と怠りのため、また周囲にいる全ての人々のため、さらには、生存している、そして、既に亡くなった全てのキリスト教信者のために、御身の不肖なるしもべである私が、捧げる、この汚れなきいけにえを受け入れ給え。それは、私と彼らとにとって、永遠の生命へと救われるために益となるためである。)
45 nutrimentum
46 "Veni, Sanctificator omnipotens aeterne Deus: et benedic hoc sacrificium tuo sancto nomini praeparatum."(聖とならしめ給うもの、全能の永遠の天主よ、来たりて御身の聖なる聖名にそなえられたこのいけにえを祝し給え。)
47 総則233番には、「ミサの中ではひざまずく表敬が3回行われる。すなわち、パンを会衆に示した後、カリスを会衆に示した後、及び拝領前」とある。ただし、日本では、跪くことが全て「合掌して深く礼をする」こととされている。例えば、総則の84番や98番、同じく233番などを見よ。また、祭壇に接吻することも「合掌して深く礼をする」こととされている。例えば、総則の85番を見よ。
48 総則103「カリスをコルポラーレの上に置き、場合によってはパラで覆う。」となっており、パラの使用は義務ではなくなっている。
49 総則294「金属製の祭器は、さびを生ずるものであれば、内側全面を金メッキしなければならない。さびを生じない金属や上等な金製のものは、金メッキの必要はない。」
50 総則265「固定祭壇であれ、可動祭壇であれ、典礼書に記載されている儀式にしたがって聖別される。ただし可動祭壇は、ただ祝福することだけ[で使用すること]が出来る。」
51 mensa
52 総則265「可動祭壇、もしくは聖堂外の祭儀が行われる机には、聖別された石を置く必要は全くない。」
53 総則268「主の記念祭儀に対する尊敬、ならびに主の体と血が供される会食に対する尊敬を表すために、祭壇上には少なくとも1枚の食卓布を敷く。」
54 grottesco ringraziamento di prete e fedeli seduti
55 reverenter accipiatur
56 quasi sarcastico
57 mensa 原注10: 祭壇のもっとも主要な機能が述べられているのは、ただ1度だけ総則の259番でしかない。"Altare, in quo sacrificium crucis sub signis sacramentalibus praesens efficitur."(祭壇は、十字架のいけにえが秘跡的なしるしのもとに現在のものとなる場所である。)しかし、これだけでは、その他の名称が頻繁に使われていることによる不明確さを消し去るには、あまりにも少なすぎる。
58 "Altare, seu mensa dominica, quae centrum est totius liturgiae eucharisticae"(n.49)
59 総則262「中央祭壇は、容易に周りを回ることが出来るよう、また会衆に対面して祭儀を行うことが出来るように、壁から離して建造する。またその位置は、全会衆の注意が自ずから集まる真に中心となる場所であるようにする。」
総則276「聖体を保存する場所は、信者の個人的な礼拝と祈りに相応しい小聖堂のなかに設置されることが切に勧められる。これが出来ない場合には、…聖体は、ある祭壇、もしくは教会堂内の、…他の場所に保存するものとする。」
60 原注11: ピオ12世教皇は、1956年9月23日、典礼大会への講話の中でこう言っている。「祭壇から御聖櫃を切り離すこと、それはその起源と本性とによって結合していなければならない2つのものを切り離すことです。」
61 原注12: 新しい式次第は「ホスチア」という言葉をほとんど使っていない。「ホスチア」という言葉は典礼書における伝統的な表現であり、「いけにえ」という正確な意味を持っている。「ホスチア」という言葉が使われていないことに、またもや、「晩餐」とか「食べ物」という観点にのみ焦点を当てようとしている計画的な同じ意志を読まざるを得ない。
62 原注13: 一つのことを別のことで置き換える、あるいは取り替える、という常套手段によって、主の御聖体における現実の現存が御言葉における現存に同一視されてしまっている(総則7「「主の晩さん、またはミサは、聖なる集会の義、すなわち『主の記念』を祝うために、キリストを代理する司祭を座長として、一つに集まった神の民の集会である。したがって、『わたしの名において、2、3人が集まるところには、その中にわたしもいる』(マテオ18:20)というキリストの約束は、特に教会がそれぞれの地域で集まるときに実現される。十字架のいけにえが続けられるミサの祭儀において、キリストは、その名のもとに集まっている集会の中、奉仕者の中、御言葉の中に、現実に、またパンとぶどう酒の形態のもとに本体のまま現存される。」及び54番)しかし、真実は、この2つのことは別の本性の事柄である。御言葉における主の現存は、それを読んでいるときにだけ、つまりそれを使うということにおいてin usu、現実のものとなる。しかし、御聖体における現存は客観的に、恒常的に、秘跡的に拝領されるか否かに関わらず、常にある。次のような言い回しは、典型的にプロテスタント的な言い方である。「説教によって提示される聖書朗読のなかで、神はその民に語られ、…キリストは、ご自身の言葉によって、信者の間に現存される。」(総則33、聖なる典礼に関する憲章33番と7番を参照)このような言い方には、厳密に言って、いかなる意味もない。なぜなら、天主が御言葉のうちに現存することは直接的ではないからである。この御言葉における現存は、人間の時間と空間に限られた精神の行為に結びついているからである。この間違った言い方による悲劇的な結論は、このような言い方によって、御聖体における現実の現存が、御言葉における主の現存のように、それを使うということに結びついているのではないかということを暗示していることである。すなわち、それを使っていなければ、つまり、御聖体拝領をしないときには、主は御聖体において現存していない、ということを暗示してしまっている。
63 Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis.
64 in mei memoriam
65 volti alla mia memoria
66 Haec…, in mei memoriam facietis.
67 Hoc facite in meam commemorationem.
68 原注14: 秘跡を執行するということは、『新しい司式』の総則の中で命令されている限りにおいて、イエズスが使徒たちにご自分の御体と御血をパンとぶどう酒の形色のもとにおいて「食べるために」与えられたという事実と同時であったということも意味されている。そのために、秘跡を執行するということは、もはや聖別という行為に存していない、すなわち、御体と御血との分離である、ということに存していない。しかし、このことにミサのいけにえという現実の本質のもののが属しているのである。(ピオ12世の回勅『メディアトル・デイ』を見よ。)
69 "naratio institutionis"
70 Ecclesia memoriam ipsius Christi agit.
71 「エピクレーシス」とは、奉献されたホスチアが聖変化するように天主の力を祈り求める教会の祈願のことである。
72 Hoc est Corpus meum
73 Hoc est Corpus Christi
74 原注15: 新しい式次第に載せられている限りにおいて、聖別の言葉は司祭の意向のお陰によって有効であり得る。しかし、この聖別の言葉は無効でもあり得る。なぜなら、もはや言葉自体の効力によって(ex vi verborum)は、有効性を失っているからである。もっと正確に言いかえると、聖別の言葉は、以前のミサにはあった言葉それ自体が意味する様式(modus significandi)が変えられてしまっているために、それに自体によっては、有効性を失っているからである。近い将来、聖伝にかなう養成を受けずに叙階される司祭たちが「教会のしていることをする」ために新しい司式に信用しきったとしたら、彼らは有効に聖変化を執行するのだろうか?この有効性に疑いを抱くことは許されている。[Le parole della Consacrazione, quasi sono inserite nel contesto del Novus Ordo, possono essere valide in virtu dell'intenzione del ministro. Possono non esserlo perche non lo sono piu ex vi verborum o piu precisamente in virtu del modus significandi che avevano finora nella Messa. I sacerdoti che, in un prossimo avvenire, non avranno ricevuto la formazione tradizionale e che si affideranno al Novus Ordo al fine di "fare cio che fa la Chiesa" con-sacreranno validamente? E lecito dubitarne.]
75 "Mortem tuam annuntiamus, Domine, etc… donec venias."(主よ、御身の来るまで、我らは御身の死を告げ知らせよう。)
76 "Quotiescumque manducamus panem hunc, et calicem bibimus, mortem tuam annu-tiamus, Domine, donec venias."
77 原注16: プロテスタント的な批判がよくやるようにこれらの表現は聖書の同じ文脈に載っている(コリント前書11:24-28)と言わないように。なぜなら、教会は異なった表現で表される異なった現実を混同しないように、常にそれらの表現を並べたり、重ねたりするのを避けてきたからである。
78 Autonoma (absoluta)
79 Missa est sacra synaxis seu congregatio populi.
80 "Qua salutatione et populi resonsione, manifestatur ecclesiae congregatae mysterium."(この挨拶と会衆の応答は、ともに集まった教会の神秘を表す。)
81 cum populo
82 sine populo
83 "populus sui sacerdotii munus exercens"(総則45番「共同祈願、すなわち信徒の祈りにおいて、会衆は、自分の祭司職の務めを実行して、全ての人のために祈る。」)
84 Prex eucharistica III
85 "populum tibi congregare non desinis ut a solis ortu usque occasum oblatio munda offeratur nomini tuo"
86 原注17: ルター派とカルヴィン派は全てのキリスト者が司祭であり、全てのキリスト者が晩餐を捧げると主張している。しかし、トリエント公会議に従えば(第22総会Canon 2 DS1752)、「全ての司祭は、そして司祭だけが、ミサのいけにえの二次的な司式者である。キリストがミサの第1の司式者である。信者も捧げるが、それは厳密な意味におけるのではなく、司祭を通して、間接的に捧げるのである。」(A. Tanquerey, Synopsis thologiae dogmaticae Descl?e 1930, t. III)
87 in persona Christi
88 "quidam de populo"
89 エピクレーシスについて、総則の55番「ハ」は、こう言っている。「この特別な祈りによって、教会は神の力を願い求め、…祈る。」
90 in persona Christi
91 原注18: キリスト教を信ずる民にとって信じられないほどの、且つ、悲惨な改革は、聖金曜日の祭服の色が黒ではなく、赤になったことである(総則308番のロ)。赤は、特に殉教者を記念する色であり、教会がその花婿であるイエズス・キリストの死を喪に服す色ではない。
92 原注19: これは、フランスのドミニコ会司祭Pere Roguet O.P.のことである。
93 "un homme un peu plus homme que les autres"
94 actio Christi et Ecclesiae
95 "Presbyter celebrans... populum... sibi sociat in offerendo sacrificio per Christum in Spiritu Sancto Deo Patri"
96 per Spiritum Sanctum Deo Patri
97 paschalismo
98 "prex eucharistica IV"
99 "pro omnibus orthodoxis atque catholicae fidei cultoribus"
100 "omnium qui te quaerunt corde sincero"
101 "cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis"
102 "obieunt in pace Christi tui"
103"Quorum fidem tu solus cognovisti"
104 原注20: ローマ・カノンの翻訳のうちいくつかは、"locus refrigerii,lucis et pacis"(すずしみと光と平和の場所)が、「至福、光、平和」という状態として訳されている。「苦しむ教会」に関して明確な言及が消え失せてしまったことについては何と言ったらよいだろうか!
105 原注21: この省略omissionの病熱の最中に、ただ一つ付け加えられた言葉がある。それは、告白の祈りのなかで罪を告白し、「思い」と「言葉」と「行い」に続けて「怠りomissio」の罪が付け加えられたことである。
106 Communicantes, et momoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andeae, Jacobi, Joannis, Thomae, Jacobi, Philipi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Thaddaei: Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Joannis et Pauli, Cosmae et Daminai: omnium Sanctorum tuorum; quorum meritis, precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.(聖なる一致をしつつ、我らは、まず、我らの天主なる主、イエズス・キリストの御母、終生童貞なる光栄あるマリアの記念を謹んで行い奉る。また更に、主の聖なる使徒かつ殉教者、ペトロとパウロ、アンドレア、ヤコボ、ヨハネ、トマ、ヤコボ、フィリッポ、バルトロメオ、マテオ、シモンとタデオ、また、リノ、クレト、クレメンテ、シクスト、コルネリオ、チプリアノ、ラウレンチオ、クリソゴノ、ヨハネとパウロ、コスマとダミアノ、および主の全ての聖人らの記念を恭しく行い奉る。願わくは、彼らの功徳と祈りとによって、我らが全てにおいて御身の保護の助力を与え給わんことを。同じ我らの主キリストによりて、アーメン。)
107 Libera nos, quaesumus, Domine, ab onmibus malis, praeteritis, praesentibus, et futuris: et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus Sanctis, da propitius pacem in diebus nostris: ut ope misericordiae tuae adjuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.(主よ、願わくは、過去、現在、未来の全ての悪より我らを救い給え。終生童貞なる永福の光栄ある天主の御母マリアと御身の至福なる使徒ペトロとパウロ、また、アンドレアとともに、全ての諸聖人のおん取り次ぎにより、おん慈悲をもって今日平安を与え給え。そは、おん憐れみの御業に助けられ、常に我らが罪から救われ、全ての惑わしから安全に守られんがためなり。)
108 原注22: 新しい司式が提示されたとき記者会見の席で、レキュイェ神父P?re L?cuyerは理性だけを信じているという「信仰宣言」をはっきりとし、会衆の参加していないミサでの挨拶は、「Dominus tecum主はあなたと共に」「Ora, frater兄弟よ祈れ。」という言い方を考えているとさえいった。これは、「作り事がなくなり、真理に適わないことがなくなるためである」(ソノママ)とのことである。
109 "tremendum mysterium"
110 "Aufer a nobis"の祈り
111 "Oramus te, Domineの祈り
112 "Aufer a nobis"
113 "Omramus te, Domine"
114 "mensa" 総則の260番には、「感謝の祭儀は、…聖堂以外の場所においては、…適当な机の上でも行うことが出来る。但し必ず食卓布とコルポラーレを備えなければならない」とある。総則の265番には「可動祭壇、もしくは聖堂外の祭儀が行われる机(260参照)には、聖別された石をおく必要はない」とある。
115 "convivium"
116 総則244番の「ニ」によると、「助祭または教会奉仕者[これは、いわゆる侍者のことである。]は、カリスとプリフィカトリウムを拝領者に差し出し、拝領者は、適宜に、自分の手で、カリスを口に持って行く。拝領者は、左手でプリフィカトリウムを口の下に保ち、こぼさないように注意しながら、少量の御血をカリスから拝領する」とある。
117 総則65:「教会奉仕者は、祭壇での奉仕と、司祭及び助祭を助けるために選任される。教会奉仕者には、特に祭具の準備をすること、及び特別奉仕者として聖体を信者に授けることが委ねられる。」
118 総則66:「聖教奉仕者は、福音を除き、聖書を朗読するために選任される。また共同祈願の意向を述べ、詩編朗読者がいないときには、朗読の合間に詩編を唱えることが出来る。宣教奉仕者は、感謝の祭儀において、固有の役割を持っている。この役割は、より上級の位階の奉仕者がいる場合にも、宣教奉仕者自らが果たさなければならない。」
119 総則67:「朗読の間にある詩編または聖書参加を朗唱することは詩編朗唱者の務めである。」
120 総則68の「イ」:「解説者=信者を祭儀に導き、よりよく理解させるために、信者に指示や説明を与える。」
121 総則68の「ロ」:「案内係=地方によっては、教会の入り口で信者を迎え、適当な席に案内し、また行列を整理する。」
122 総則68の「ハ」
123 総則68「また、ミサ典礼書、十字架、ろうそく、パン、ぶどう酒、水、香炉を運ぶ者がある。」
124 mulier idonea 総則70:「助祭に固有な役務以外の役務は、選任を受けていなくとも、男子信徒が行うことが出来る。司祭席の外で行われる役務は、…女子にも委ねることが出来る。」
125 "ministeria quae extra presbyterium peraguntur"
126 原注23: このことに関して、今ではたとえ司祭が共同司式の前或いは後に一人でミサを捧げなければならない時でさえも、司祭はもう一度共同司式の時に両形色で聖体拝領することが合法的になってしまったようである。
127 原注24:「ヒッポリトのカノン」として提示されたが、実際はいくらかの言葉がそのまま使われているだけで何も残ってはいない。
128 原注25: "Gottesdienst" no.9, 14 Mai 1969
129 原注26: ビザンチン典礼に於いて見いだされる次の要素を考察せよ。長い何度も繰り返される悔悛の祈り。司式司祭と助祭の祭服を着るための荘厳儀式。プロスコメディアという捧げものの準備のそれ自体で完全な一つの典礼様式。たとえ奉献の祈りの最中であっても聖母や諸聖人への何度も繰り返される祈祷。福音を読むときに「目に見えない共同司式者」としての天使の諸階級への祈り。聖歌隊はケルビコンと名付けられ、天使の階級の一部と見なされている。聖所を教会のその他の部分と区別し聖職者を平信徒と分離させる至聖所の幕(イコノスタシス)。全典礼がそれへと意味付けられている天主の神秘を象徴する隠れた聖変化。天主へと面し決して会衆に対面しない司式司祭の姿勢。聖体拝領は必ず司式司祭によってのみ配られること。聖変化した両形色に対する絶えざる礼拝の印。会衆の本質的に観想的な態度。東方典礼に於いてはたとえそれがあまり荘厳でない様式に於いてでも1時間以上続き「敬虔の念を起こさせ、言語を絶する、・・・天的な、命を与える神秘」として常に定められている。また、ローマ・ミサに於いてそうであったように、聖ヨハネ・クリソストモの典礼と聖バシリオの典礼に於いて、いかに「晩餐」や「会食」の考えがいけにえの考えに明らかに従属しているかということを最後に記しておく。
130 "Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum."
原注27: トレント公会議第23総会に於いて(御聖体についての教令に於いて)その宣言の目的をこう定義した。「御聖体の使用と礼拝についての信仰の教えに於いて、この宿命的な時代に於いて敵がまいた排斥されうる誤謬と離教の毒麦を完全に根こそぎにするため。主は御聖体によって全てのキリスト者を一つにまとめ結びつけようと望まれ、我らの主はご自分の教会に一致と愛との象徴として御聖体を残された。」(DB.873)
131 ティモテオへの第一の手紙6:20「おまえに委ねられたものを守れ。新奇な言葉に惑わされるな。」
132 原注28: ピオ12世回勅『メディアートル・デイ』1. §3には、こうある。
「心と魂によって、教会の典礼の起源にまでさかのぼることは、賢明なこと、ほむべきことである。典礼の研究、特にその起源の研究によって、祝日の意味や、用いられる式文の意味、教会の儀式の意味をより深くより正確に知ることが出来る。これに反して、何が何でも全てを古代の状況に戻そうとするのは、賢明でもないし、賞賛すべきことでもない。例えば、祭壇のもとの形を復興しようとしてテーブルのこれに変えようとするもの、祭服には決して黒色を用いないと言う人々、聖画や聖像を聖堂から取り除こうと言う人々、救い主がお受けになった激しい苦難を表さないような十字架を要求する人々、そして使徒座から与えられた規定に合っているのに混声音楽を非難したり否定したりする人々は、正しい道から外れている。…このような思想や態度は、非合法なピストイアの教会会議があおり立てた不健全な考古学主義を復興させようとするものであり、またそれは、この会議を不法なものとし、人々の霊魂に大きな害を与えた種々の誤謬を復古しようとするものである。天主である創立者から委ねられた「信仰の遺産」の常に忠実な守護者である教会は、当然のことながらそれを否定した。」
ここで、ピオ12世は、1794年8月28日ピオ6世が発布した使徒憲章Auctorem Fideiを参照させている。たとえば、
(33)「ピストイア会議は、典礼に関する諸原則の一部を忘れてきた原因を除くために、『儀式の簡素化、自国語による典礼、声高く唱えること』を望んでいる。こうして、教会によって認められている現行の典礼は、諸原則の一部を忘れたことから導入されたかのように主張している。…この命題は軽率、信心深いものを傷つけ、教会を傷つけ、教会を攻撃する異端者を助長する。」(DS2633)
また、(66)には、「『信徒が全教会と声を合わすようにしなければ、それは使徒自体の実践と天主の勧めに反することである』と主張することは、すなわち、典礼上の祈祷に国語の使用を取り入れようとすることは、誤りであり、軽率であり、諸秘義の執行の秩序を乱すものであり、数多くの悪弊を導入するものである」とある。
133 原注29: パウロ6世回勅『エクレジアム・スアム』1964年4月3日
134 原注30: パウロ6世、1969年4月3日聖木曜日の説教「実際上離教的なパン種が、教会を分裂させ、分断し、粉々にしています。」
135 原注31: パウロ6世、同じく、1969年4月3日聖木曜日の説教「私たちが今読んだばかりのコリント人への第1の手紙の中で聖パウロが優しく告発しているこの離教とこの分裂が私たちの中にもあるのです。」
136 原注32: 第2バチカン公会議について、よく知られた事実が、現在、自ら自分がその教父であったと自慢している人たちがこの公会議を否定していることである。彼らは公会議の内容を「爆発させよう」と決心して公会議を終えて帰路についた人たちである。反対に、教皇聖下は閉会の時に、この公会議はいかなる変化をも導入しなかった、と宣言された。不幸なことに聖座は、「聖なる典礼に関する憲章の実行のための委員会」を仲介にして、説明の出来ないほどの早さで、公会議の文章に不忠実であることを(しかもこの不忠実さは日増しに増加ばかりするのであるが)許し、しかも推奨している。この不忠実さは、見かけ上はただ単に形式的なものに過ぎない変更(ラテン語、グレゴリオ聖歌、尊敬を払うべき典礼様式、等々)から信仰の実体に触れさえする様々な変更にまで至っている。私たちがこの研究によって明らかにしようとした恐るべき結果は、また更に心理学上より劇的に、規律の部門において、またキリスト教会の教導権の分野において、影響を及ぼしており、それと同時に、聖座が持つ名誉ある地位とこれに払わなければならない従順とを揺るがしてしまっている。
![]()
![]()